お正月といえば、初日の出を拝んだり、初詣に出かけたりと、新しい年の始まりを迎える大切な行事が多くあります。その際、天気が気になるものの、ほとんどの人が心配していないのではないでしょうか。理由は、毎年お正月は晴れているような気がするからです。しかし、これはただの気のせいではありません。実際に太平洋側は冬に晴れやすいのです。
今回は、気象庁のデータを元に、お正月の天気が本当に晴れやすいのかを検証し、太平洋側と日本海側の気候差についても掘り下げていきます。
太平洋側の「晴れやすさ」
東京を例に、1967年から2018年の52年間の1月1日から3日の天気データを分析したところ、晴れまたは快晴の日が86日と、過半数を占めていました。これに「晴れ時々曇り」などを含めると、その数字はさらに増加します。平均雲量は4.03で、これは雲が少ないことを示しています。名古屋でも同様に、52年間で晴れや快晴の日が69日、平均雲量は5.63と、晴れが多い傾向が見られます。
一方で、同じ期間に新潟で晴れた日は非常に少なく、快晴の日はゼロ、晴れの日もわずか7日、平均雲量は8.98でした。東京や名古屋に比べて、いかに曇りや雨の日が多いかがわかります。
太平洋側と日本海側の気候差
太平洋側は「太平洋岸式気候」と呼ばれ、冬は乾燥して晴れが多いのが特徴です。対して、日本海側は「日本海岸式気候」で、冬の降水量が多く、雪も多く降ります。この違いは、冬の気圧配置に原因があります。
シベリア高気圧がもたらす冬の気候
冬になるとシベリア付近に「シベリア高気圧」が発生します。この高気圧は、冷たく乾燥した空気でできており、日本に向かって季節風を吹かせます。その風が日本海を渡る際、海からの水蒸気を吸収し、湿った風に変わります。この風が日本列島の山脈にぶつかると、日本海側に雪を降らせるのです。
そのため、日本海側は冬に雪が多く、すっきり晴れることが少ないのです。一方、太平洋側では、この湿った風が山を越えると再び乾燥した風となり、晴れやすい状態を作り出します。この現象が、太平洋側での「晴れの正月」の正体です。
冬の雷と雪の珍しい現象
日本の冬の特徴として、日本海側では積乱雲が発生し、雷を伴うこともあります。特に冬の雷は夏の雷よりもエネルギーが強く、非常に珍しい現象とされています。世界的にも日本海側のように雪と雷が共存する地域は少なく、日本ならではの気象現象です。
まとめ
結論として、太平洋側のお正月が晴れやすいのは、冬の気圧配置と地理的条件によるものです。シベリア高気圧と日本列島の山脈が作り出す気象パターンにより、太平洋側は冬に乾燥して晴れやすくなります。
気象庁のデータに基づいても、太平洋側に住む人にとって「正月は晴れる」という感覚は、単なる気のせいではなく、事実であることが証明されます。


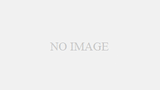
コメント